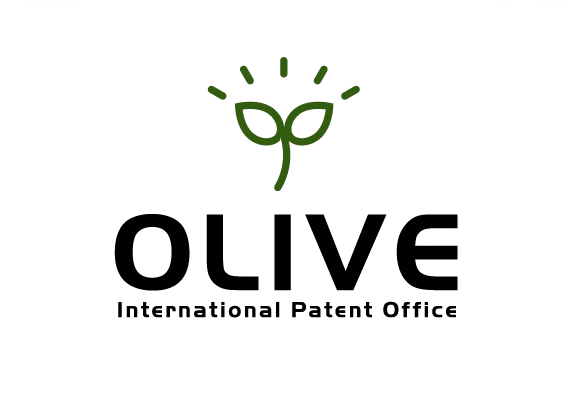NEWS
新着情報
<弁理士コラム>国境を越えたインターネット上での商標の使用について
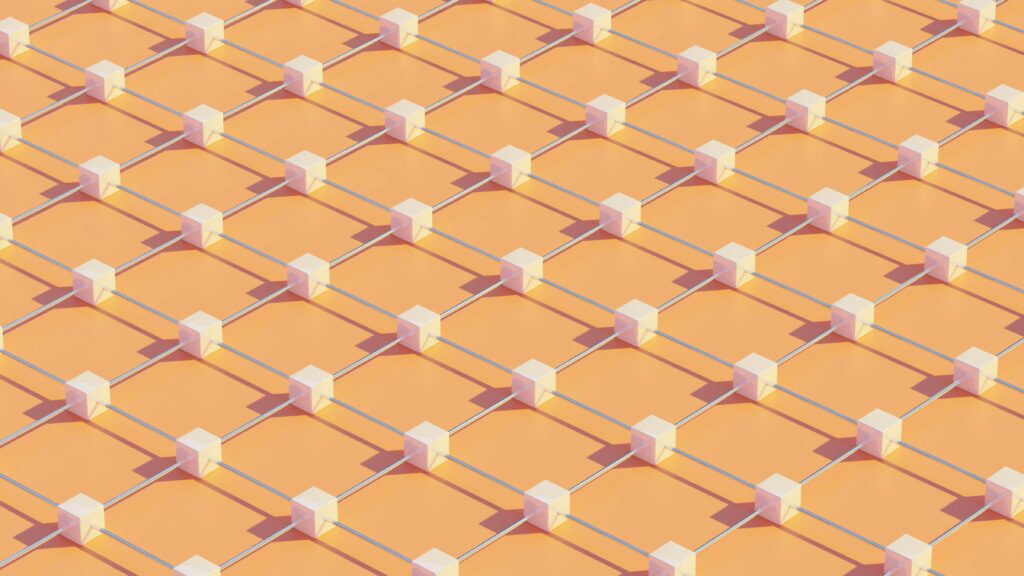
国際的なガイドライン「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(共同勧告)の内容は、以下のとおりです。(特許庁のウェブサイトより)
なお、本共同勧告は、条約のような強制力はもたないものの、各国がガイドラインとして考慮することができるとしています。
(1)インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、「商業的効果(commercial effect)」の有無によって判断する。
(2)インターネット上の標識の使用者に、事前に世界的なサーチ義務を負わせることは、当該標識の使用者に過度の負担を課すこととなり不適当であるとの前提のもと、「通知と抵触の回避」手続(”notice and avoidance of conflict” procedure)を規定する。
(3)サイバースクワティングのようなバッドフェイス(bad faith)による使用の場合を除き国の領域を超える差止命令(global injunction)を禁止する。
「商業的効果を決定するための要因」(第3条)の概要(一部)
・特定国(ウェブサイトを開設している国以外の国)でビジネスを行っている又はビジネスを行うための重要な計画に着手した旨を示す状況があるか否か(第3条(1)(a))
・特定国で実際に商品の販売やサービスの提供等があるか否か(同項(b)(i))
・特定国向けでないことを表示しているか否か(同項(b)(ii))
・特定国で保証又はアフターサービスがあるか否か(同項(b)(iii))
・特定国の通貨で価格が表示されているか否か(同項(c)(ii))
・双方向の通信手段でアクセス可能か否か(同項(d)(i))
・特定国での住所、メールアドレスなどの連絡方法が表示されているか否か(同項(d)(ii))
・特定国の言語が使用されているか否か(同項(d)(iv))
・ウェブサイトを開設している国で商標権を有しているか否か(同項(e)(i))
「通知と抵触の回避」手続(第9~12条)の概要
・商標権の取得及びその使用が悪意でないことなどの要件を満たす場合、侵害通知を受け取る以前の侵害に対しては責任を負わない。(第9条)
・侵害通知後、速やかに商業的効果の回避等の措置を行っているなどの要件を満たす場合、その使用者は責任を負わない。(第10条)
・使用者が、侵害されている旨を主張する権利の所有者と何ら関係がない旨をディスクレームしている場合、特定国はそのディスクレーマーを受け入れる。(第11条)
国境を越えたインターネットでの商標の使用については、事案にもよりますが、おおむね上記を考慮して対象の外国での使用に該当するか否かを検討できると思います。
例えば、オンラインショップのサイトにおいて、言語が日本語であり、日本円のみで表示され、日本での販売が明示されている場合は、外国に住む人がそのサイトを閲覧し購入する行為については、その外国での商標の使用に該当しない可能性があります。
ただし、いわゆる越境ECサイトの場合は、対象の外国に対して発信することを前提としていると考えられますので、当該外国の商標権を侵害することが想定されます。越境ECサイトを開設の際は、事前に対象国での商標の調査や商標登録の検討は必須であるといえます。
なお、令和6年の知財高裁において、この共同勧告を示して(補足的に)、日本語でのウェブサイトでマレーシアの寿司店舗名を掲載する行為について、日本での商標の使用には該当しないと判断した例があります。この判決例では、主に証拠の認定が重要であったと考えますが、実質的な影響(商標の機能が害されていないこと)や属地主義の原則の他、共同勧告における商業的効果の認定も影響していると考えられます。
リンク:
「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf
特許庁「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
知財高裁判決
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/093478_hanrei.pdf
弁理士 翠簾野哲