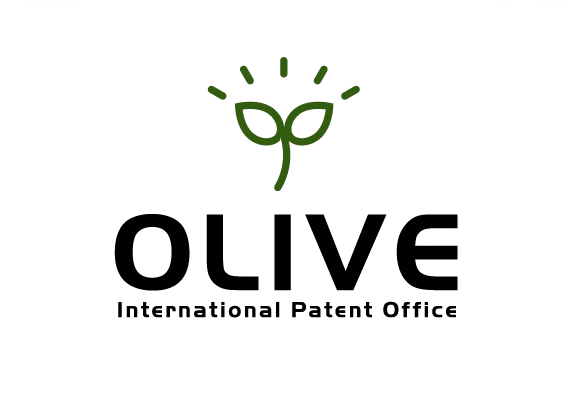NEWS
新着情報
<弁理士コラム>ChatGPTと特許業務の未来(第1回)

ChatGPTが2022年11月に登場してから約2年が経過し、特許業務にも活用されるようになりました。特に、言語処理能力の向上には目を見張るものがあります。文章作成の精度が高く、技術的な背景を短時間で調査できるため、発明の技術的説明を補助するツールとして有用です。また、調査結果の妥当性についても、ChatGPTを活用して迅速に確認できるため、業務の効率化が進んでいます。
ChatGPTのメリット
ChatGPTは、技術的な文章の作成や翻訳において高い精度を発揮します。従来、時間をかけて推敲していた文書も、短時間で自然な文章に仕上げることが可能になりました。そのため、特許明細書の下書きや、技術的な文献の要約などの作業が格段に楽になりました。また、異なる言語での特許関連情報の取得が容易になり、国際的な特許業務にも貢献しています。
さらに、ChatGPTの活用は単なる文書作成にとどまりません。関連技術の概要を素早く把握し、類似技術をピックアップするのに役立ちます。従来の検索システムでは見落とされがちな情報にもアクセスしやすくなり、効率的に技術的な理解を深めることが可能になりました。
ChatGPTのデメリット
一方で、ChatGPTの弱点も見えてきました。例えば、ユーザーが求める情報を勝手に省略したり、逆に冗長に記載したりすることがあります。また、プロンプト(指示文)を工夫しても、必ずしも期待通りの結果が得られないことも少なくありません。特に、画像生成においては、テキスト生成以上にその傾向が顕著であるように感じます。
また、特許明細書などの厳格な表現を求められる文書においては、微妙なニュアンスの違いが結果に大きく影響することがあります。AIが生成した文章が法的に適切であるかどうかの最終判断は、やはり人間の専門家によるチェックが欠かせません。このため、現時点ではAIを補助ツールとして活用しながら、適切なフィードバックを与えて改善していくことが求められます。
特許業務の今後の展望
現在のLLM(大規模言語モデル)の技術では、人が意図した通りにAIが出力することは難しい面があります。技術の進化によって、AIがより精密にユーザーの意図を反映できるようになる日が来るのでしょうか。
特許業務においては、より高度なAIが開発されれば、発明の創出から特許取得、さらには権利行使までの一連のプロセスが一層スムーズになる可能性があります。例えば、AIが特許文書のドラフト作成だけでなく、発明者のアイデアを解析し、適切なクレーム構成を提案するような機能が実装されれば、弁理士の業務効率は飛躍的に向上するでしょう。
以上、まとまりすぎた当たり前の内容だと思われたかもしれません。そこで、いくつかの視点を提案したいと思います。
1. AIのアウトプットは人間の意図を完全に汲み取れないが、それが逆に創造性を生むこともある
・例えば、ユーザーが求めていない情報をChatGPTが加えることがありますが、それが新しいアイデアのヒントになる場合があります。
・AIのミスが、思わぬ発明のインスピレーションになる可能性もあります。
2. 「AIがミスをすること」自体が、弁理士の価値を高める
・AIが完全に正確ではないため、専門家による最終判断が不可欠となり、弁理士の仕事が一層大事となります。
・AIの活用には「AIによって仕事が奪われる」よりも「コンピュータと人間の役割分担がより明確になる」という側面があります。
3. 特許明細書の作成において、AIが“不完全”な文章を出力することで、人間のチェックが容易になる可能性がある
・AIが完璧な文を作ってしまうと、逆に人間がどこを直せばよいか分からなくなるといえるかもしれません。
・曖昧な部分が残っていることで、弁理士の視点から最適な修正を加えやすくなるという効果がありそうです。
このように、AIの活用には、単なる効率化だけでなく、新しい発想を生むツールとしての可能性も秘めています。今後もAI技術の発展を見守りながら、より創造的な活用法を模索していきたいと考えています。
とはいえ、もしこのコラムの内容に突飛なところや、ぎこちないところがあると思われたなら、それは私がコラム執筆にあたってAIに頼りすぎた証拠です。
弁理士 三苫貴織